 ぬん
ぬんこんにちは
ミニマリスト ぬん です
ミニマリストを目指す過程で学んだ
少ないモノで、心地よく暮らすヒントをお届けしています。
はじめに
片づけをするときに必ず直面するのが、「なんとなく捨てられない」モノの存在です。


私自身も、子育てや仕事に追われながら暮らしていると、
どうしても家の中にモノが増えてしまい、
いざ片づけを始めてもなかなか手が止まってしまう瞬間があります。



「もう使っていないけど、もったいなくて捨てられない」
「思い出があるから手放せない」
そんなモノたちが押し入れやクローゼットの奥に眠っている方は多いのではないでしょうか。
今回は、「捨てられない」と思ったときの対処法についてお話ししたいと思います。
「直感」と「思考」がぶつかるとき


人がモノを手放すかどうかを決めるとき、2つの方法があります。
- 直感による判断
- 思考による判断
直感はシンプルです。
手に取った瞬間に「これは好き」「これはもういらない」と感覚でわかる。
一方で、思考はやっかいです。
直感では「いらない」と思っても、頭の中でこんな声が聞こえてきます。


- 「まだ使えるし、もったいない」
- 「いつか必要になるかもしれない」
- 「買ったとき高かったから捨てにくい」
結果として、片づけは進まず、モノは積み上がっていく一方です。
手放せないのは悪いことではない
誤解してほしくないのは、
「捨てられない」こと自体が悪いわけではないということです。
モノに思い入れがある証拠でもあり、
直感だけですべてを切り捨てられる人なんて、ほとんどいません。


大切なのは、ただ「もったいないから捨てられない」で終わらせず、
そのモノにしっかり向き合うことです。
モノの役割を考えてみる
「なぜ、私はこれを持っているのだろう?」
「このモノは、私にどんな役割を果たしてくれたのだろう?」
そう問いかけると、モノを見る目が変わってきます。
例:着なかった服の場合


クローゼットの中に、買ったけれどほとんど着なかった服があるとします。
- 買ったとき:「かわいい!」「似合うはず!」とワクワクして買った → 買う瞬間にときめきをくれた役割
- 着なかった理由:「実際には似合わなかった」
- 得られたこと:「自分にはこの色や形は合わない」と学んだ
つまり、その服は「学び」という役割を果たしてくれているのです。
だからこそ、「ありがとう」と感謝して手放すことができるのです。


モノと人との関係は似ている
モノとの関係は、人との出会いや付き合い方にとてもよく似ています。
人生の中で出会う人すべてが、親友や大切なパートナーになるわけではありませんよね。


同じように、家に迎え入れたモノすべてが「一生大事に使うモノ」になるわけでもありません。
ある人との出会いが、「短い時間だけど楽しかったな」という記憶を残してくれることがあります。
また、「この人は自分と合わなかった」と感じる関係が、
結果的に「自分にとって大切にしたい人はこういう人なんだ」と気づかせてくれることもあります。
モノもまったく同じです。
たとえば、ほとんど使わなかった家電や、数回しか着なかった服。
それらは「失敗した買い物」と片づけられがちですが、
実際には「自分にとって合わないモノを知る」という役割を果たしてくれています。
人との関係に「学び」があるように、モノとの関係にも必ず「気づき」があります。
だからこそ、すべての出会いを「長く続かなかったから失敗」と捉える必要はないのです。
また、人間関係でも「距離感」が大事なように、モノとの距離感も大切です。
たとえば、久しぶりに会うと嬉しい友人がいるように、
「たまに取り出して使うだけで十分役割を果たしてくれるモノ」もあります。
逆に、いつも一緒にいるからこそ安心できる家族のように、
「毎日そばにあるから生活が成り立つモノ」もあります。
こうして考えると、モノも人と同じように、それぞれ役割や距離感が違うのです。
そして一番大切なのは、出会いに意味があること。
「この人と出会ったからこそ、今の自分がある」と思えるように、
「このモノと出会ったからこそ、今の暮らしがある」と感じられる。
そんな視点でモノを見つめると、「捨てられない」と思っていたモノも自然に手放せるようになります。
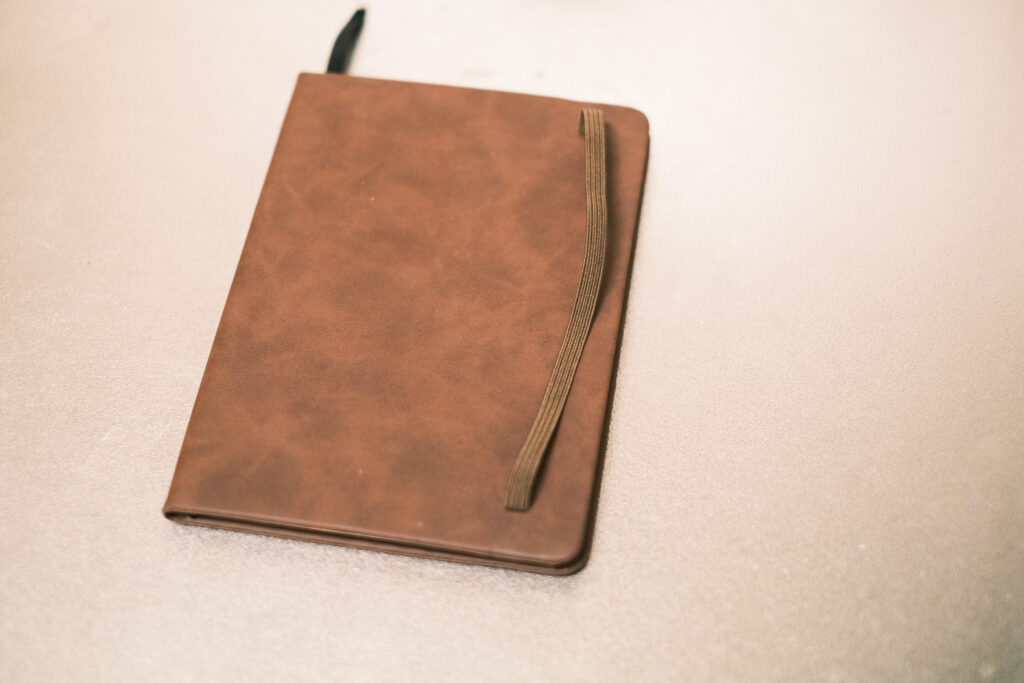
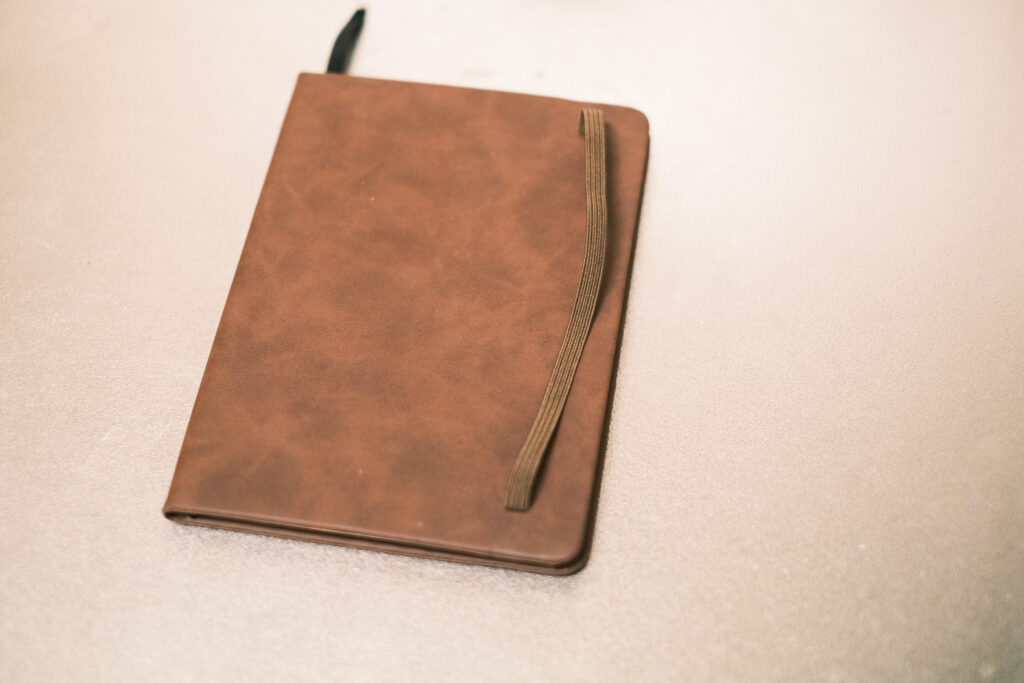
趣味嗜好は移り変わる
「昔は大好きだったけど、今はもう使わない」
そんなモノが家の中に眠っていませんか。
人の趣味や好みは、年齢やライフスタイル、そして家族の形によって大きく変わっていきます。
独身のときに必要だったモノが、結婚後にはほとんど出番がなくなったり、
子どもが生まれてからは優先順位がガラリと変わったり。
私自身も、20代のころは「おしゃれで持っているだけで気分が上がるモノ」に価値を感じていました。
でも、30代になり子育てが始まると、
「使いやすい」「片づけやすい」「長く使える」といった基準でモノを選ぶようになりました。


その結果、以前は手放せなかったモノも、
「もう今の私たちの暮らしには合わないな」と感じるようになったのです。
だから、「捨てられない」と思ったモノに対しても、
「今の自分や家族にとって必要か?」という視点で見直すことが大切です。
過去には必要だったけれど、今は役割を終えたモノかもしれません。
我が家の習慣:ひと月に一回の点検


私の家では、ひと月に一回、家の中のモノを点検する時間をつくっています。
大げさな片づけではなく、クローゼットや棚をサッと確認して
「これ最近使ったかな?」「もう役目を終えていないかな?」と見直す程度です。
この小さな習慣があるだけで、モノが積み上がるのを防げますし、
「気づいたら家がパンパン」という事態にもなりません。
また、夫婦で一緒に点検することで、
「これ、まだ必要?」「これは手放してもいいよね」と会話が生まれるのも大きなメリットです。
趣味嗜好やライフスタイルは変わっていくもの。
だからこそ、暮らしに合わせてモノを見直す時間を持つことが、心地よい生活につながるのだと思います。
「捨てる」は粗末にすることではない


「たくさん捨てる=モノを大事にしていない」と思ってしまう人も多いでしょう。
でも、本当にそうでしょうか。
押し入れやタンスの奥で忘れ去られたまま、
ほこりをかぶっている状態は「大切にしている」といえるでしょうか。
もしモノに気持ちがあるなら、きっと悲しいと思います。
だからこそ、「ありがとう」と感謝して解放してあげることが、
本当の意味でモノを大切にすることにつながるのだと思います。


子育て世代こそ、モノとの関係を見直すタイミング
30代で子育て中の私にとって、「捨てられない」と向き合うことは日々の課題です。
子どもの成長とともに増えるモノ。
ベビーカー、ベビー服、おもちゃ……。


「思い出があるから」と取っておきたくなる一方で、家のスペースには限りがあります。
だからこそ、モノが果たした役割を考えて、感謝して手放すという習慣が必要になります。
「この服は、子どもが産まれた時期に着させていたな」
「でも今はもう着れなくなった。成長の一部を支えてくれてありがとう」
そう思って手放すと、不思議と罪悪感は薄れていきます。
まとめ:モノに片をつけるということ


「捨てられない」と思ったモノこそ、丁寧に向き合ってみる。
役割を見つけ、感謝して手放す。
そうして残ったモノは、
これからの暮らしを一緒に支えてくれる本当に大切な存在です。
片づけでスッキリするのは、人だけでなくモノにとっても同じこと。
役割を終えたモノを解放することは、私たち自身の気持ちも軽くしてくれます。
「捨てること」は終わりではなく、新しい暮らしを始めるための一歩。


子育てや仕事で忙しい毎日の中でも、
モノとの関係を整えることは、
暮らし全体を心地よくする大切な習慣だと私は感じています。










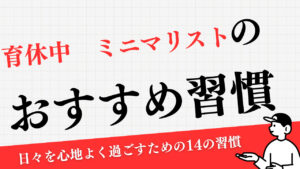
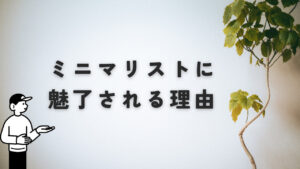
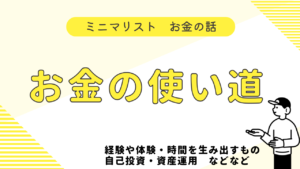
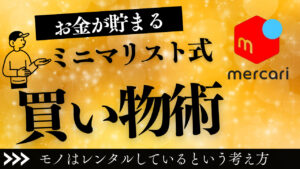

コメント